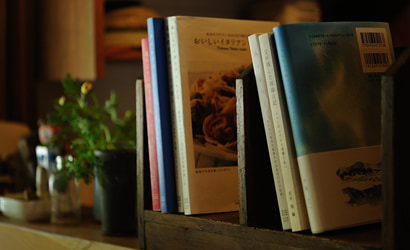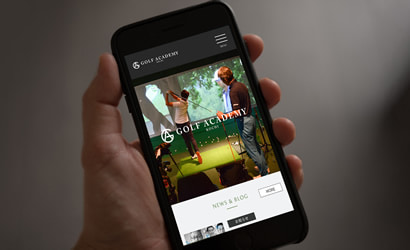REPORT「土佐の植物暦」山好き社員の散策レポート
「土佐の植物暦」
山好き社員の散策レポート
No.15

日中の暑さが和らぎ、早朝はヒンヤリしてきました。朝の涼しいうちに近くの里山へ。草原を歩くと靴や足もとがびっしょり濡れました。空は晴天、夜来の雨もなかったのに‥。
しゃがむと辺り一面の草に朝露が付いていました。葉の表面で水玉状になった露や、霧吹きで吹きかけたような細かな露も。陽光がさすと白く光って見えます。
そういえば、この時季は「白露(はくろ)」とも。涼やかな語感が初秋のイメージを想わせます。


朝露に覆われて
朝露で濡れた草むらに鮮やかなコバルトブルーの花がひときわ目につきました。ツユクサです。花びらは2枚に見えますが、「土佐の植物暦」によると、白く小さい花びらがもう1枚―。よく見ると確かにありました。長く伸びた雄しべの下に隠れるようについています。
遠い記憶をたどると、小学校でツユクサの花の絞り汁からブルーの色水を作った実験を思い出します。ツユクサは古来、「つきくさ」とも呼ばれ、染め物の下絵を描く染料にも使われてきたそうです。

夏の名残と秋の気配
野山に初秋の気配が漂いはじめましたが、夏の名残もあちこちに。センニンソウやコガンピ、ノリウツギ、本では8月暦掲載の花がまだまだ咲いています。センニンソウは夏を惜しむように甘い香りを放っています。
その一方でマルバヤハズソウ、マルバハギ、ノアズキ、ツルボ、シシウドなど初秋を感じさせる9月暦の草花も。過ぎゆく夏と、少し遠慮がちな小さい秋が重なりながら、季節はゆっくりと移ろっています。

優雅なたたずまい
嶺北で偶然みつけたシシウドには目を見張りました。車がやっと通れる山道に入ると、森閑とした木立のはずれで人の背丈ほどの凜(りん)とした立ち姿。茎の先端に多数の白い花が日傘のように広がっています。
近寄ると、花の枝が放射状に伸び、白いレースの編み物を広げたようです。薄緑色の袋状の葉は「つぼみ」を包んでいるのだと、帰宅後に本で知りました。
小さな袋がやがて生み出す優雅なたたずまい。本を繰りながら、あらためて豊かな気持ちにしてくれました。
「土佐の植物暦」
山好き社員の散策レポート
一覧


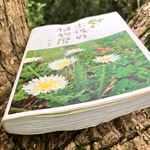 No.27・最終回(2022年7月)
No.27・最終回(2022年7月) No.26(2022年6月②)
No.26(2022年6月②) No.25(2022年6月①)
No.25(2022年6月①) No.24(2022年5月②)
No.24(2022年5月②) No.23(2022年5月①)
No.23(2022年5月①) No.22(2022年4月)
No.22(2022年4月) No.21(2022年3月)
No.21(2022年3月) No.20(2022年2月)
No.20(2022年2月)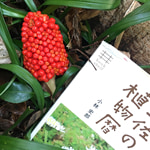 No.19(2022年1月)
No.19(2022年1月) No.18(2021年12月)
No.18(2021年12月) No.17(2021年11月)
No.17(2021年11月) No.16(2021年10月)
No.16(2021年10月) No.15(2021年9月)
No.15(2021年9月)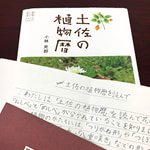 No.14(2021年8月)
No.14(2021年8月) No.13(2021年7月②)
No.13(2021年7月②) No.12(2021年7月①)
No.12(2021年7月①) No.11(2021年6月②)
No.11(2021年6月②) No.10(2021年6月①)
No.10(2021年6月①) No.9(2021年5月②)
No.9(2021年5月②) No.8(2021年5月①)
No.8(2021年5月①)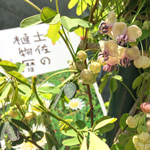 No.7(2021年4月)
No.7(2021年4月) No.6(2021年3月)
No.6(2021年3月) No.5(2021年2月)
No.5(2021年2月) No.4(2021年1月)
No.4(2021年1月)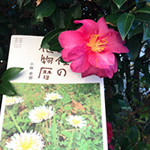 No.3(2020年12月)
No.3(2020年12月) No.2(2020年11月)
No.2(2020年11月) No.1(2020年9月)
No.1(2020年9月)